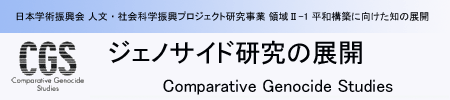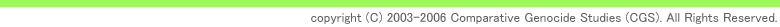第8回CGSワークショップ
<若手研究報告>
日程・会場他
・日時: 2004年7月16日(金) 17:00-19:30
・場所: 東京大学・駒場キャンパス 8号館3階306号室
プログラム
◇司会: 深川美奈(中央大学経済学部非常勤講師、CGS事務局
■報告①: 伊東直美(東京大学大学院総合文化研究科博士課程)
「『国民』のアイデンティティー生成-ドイツにおける1913年国籍法改正過程-」
■報告②: 兼清順子(一橋大学大学院社会学研究科博士課程)
「ラファエル・レムキンによるジェノサイド論」
◇コメンテーター: 増田好純(東京大学大学院総合文化研究科博士課程、CGS事務局)
報告要旨①:伊東直美
「『国民』のアイデンティティー生成-ドイツにおける1913年国籍法改正過程-」
2000 年の改正によって、ドイツ国籍法には新たに出生地主義の要素が加味された。このことがドイツ近現代史における大きな転換とみなされたことは記憶に新しい。長らく、出生地主義を導入しているフランスに対して、純粋な血統主義をとるドイツの国籍法は対置して考えられてきた。また、この排他的な血統主義はドイツの国籍、市民権の取得の際に伝統的な原則であり、さらに、このことがナチズム体制におけるジェノサイド政策を容易にしたとまで言われてきた。この原則がよりはっきりと打ち出されたとされるのが 1913 年の国籍法の改正であり、国外に住むドイツ人にドイツ国籍を保持することが認められる一方で、ドイツに生まれ育ってもドイツ人の親を持たなければ基本的にドイツ人にはなれないということが定められた。しかしながら、最近の研究では、フランス型、ドイツ型の国民概念が存在し、それが国籍に反映されたと言うのではなく、むしろドイツとフランスが互いに歴史の中で対立する形をとりつつ、国籍に関する規定を選択して行ったことが明らかにされている。
それでは排他的な血統主義の原則がドイツの国籍法の伝統ではないとすると、どのような状況が 1913 年の国籍法改正の方向性を決定付けたのであろうか。まず、国籍法改正に影響を与えたとされるナショナリスト団体の活動から、改正の要求が出され具体化する過程を分析すると、そこでは常にドイツの地勢的な特殊性と「東方からの脅威」が議論されていた。全ドイツ連盟、在外ドイツ人協会といったナショナリスト団体は、この「東方からの脅威」論と国外に住むドイツ人からの情報を組み合わせて国内外の「ドイツ民族の危機」を煽り、ポーランド系をはじめとする東欧からの移民の国籍取得を困難にするような法案改正を要求したのである。さらに、帝国議会における国籍法改正の議論に目を向けると、そこでは国籍取得の規定とともに、国外に住むドイツ人に対する国籍の保持に関する規定が焦点となっていたことが分かる。保守党や帝国党、国民自由党の多くの議員は不変性を伴う「民族」に基づく「民族としての国民」を想定し、社会民主党と左派リベラルは義務と権利に基づく共同体を想定していた。この議論において、当時の統一ドイツがいかに、階層、宗派、地域ごとに多様であったかが浮き彫りにされている。
すなわち、 1913 年の国籍法は、ドイツの伝統的な国籍の概念の帰結というよりは、新たな出発点であった。 1871 年の統一後、「未完成の国民国家」をどのような共同体として考えるかが、国民を統合するために不可欠な問題となっていた。結果として、 1913 年改正国籍法は、「民族共同体」としてのドイツ国民国家を規定したものとなった。しかし、この改正を従来の民族的観点の強化として捉えることは必ずしも妥当ではない。そこでは、ドイツ社会の内部対立と、ドイツ国内と国外の関係が影響しており、多様な「国民像」は部分部分で重なりつつ、ドイツ「国民」という党派を超えたコンセンサスをつくりあげていったのであった。