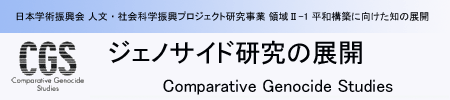��U��b�f�r���[�N�V���b�v
�u�����̗}�~�ƍ��ېl���@�v
���u�n�挤���ɂ��l�Ԃ̈��S�ۏ�w�̍\�z�v�Ƃ̋���
�����E��ꑼ
�E�����F�@2004�N6��12���i�y�j 13:50�|18:00 �i13:00�J��j
�E�ꏊ�F ������w�E���L�����p�X�w�ی𗬓� 3F �w�ی𗬃z�[��
�v���O����
�����A�F�@���؉p�[�i�����O�����w�j
����|�����E�i��F�@�����O�Ɓi������w�j
���@�F�@�A���z�q�i�c��`�m��w�j�u�A�[���o�C�W�����ɂ����閯���̏����v
���A�F�@���S���q�i������w�j�u�}�C�m���e�B�̌����̍��ۓI�ۏ�v
���B�F�@�ċX�O�i������w�j�u���[�S�X�����B�A�����Ɩ��������v
���R�����e�[�^�[�F�@�y���O�V�i�_�ˑ�w�j
�v�|
�E�@�F�@�A���z�q�u�A�[���o�C�W�����ɂ����閯���̏����v
�E�A�F�@���S���q�u�}�C�m���e�B�̌����̍��ۓI�ۏ�v
 �v�|�@�F�@�A���z�q�i�c��`�m��w�j
�v�|�@�F�@�A���z�q�i�c��`�m��w�j
�u�A�[���o�C�W�����ɂ����閯���̏����v
�@�A�����j�A�l�̓g���R�l�ɂ��ߎS�Ȗ����s�E���Ă����Ƃ������Ƃ��L���Z�����Ă������A�A�����j�A�l�������s�E�̉��Q�҂ł�����A�A�[���o�C�W�����l�����̔�Q�҂ł���Ƃ������ʂ͂��܂�m���Ă��Ȃ��B�A�[���o�C�W�����ł́A���N�A 3 �� 31 �����u�W�F�m�T�C�h�L�O���v�Ƃ��i 1988 �N�̑哝�̗߂ɂ��j�A�W�F�m�T�C�h�̔�Q�҂Ƃ��ẴA�[���o�C�W�����l�̗��j���ĂыN�����A�����̈ӎ��ɋ����A������ƂƂ��ɁA���O�I�ɂ��A�s�[�����s���Ă���B
�@�A�[���o�C�W�����l�ƃA�����j�A�l�̊Ԃ̑Η���\������ɂ�����A�����A�W�F�m�T�C�h��|�O�����Ƃ������t���p�����Ă����B�����A�A�����j�A�l�ɑ���W�F�m�T�C�h�ƌ����Ă���u�X���K�C�g�����v�̃A�����j�A�l���҂� 26 �l�ł��邱�Ƃ���ӂ݂Ă��A�ǂ̂悤�ȏo�����ɂ��āA�����Ȃ��Ɋ�Â��ăW�F�m�T�C�h�ł���Ƃ����F����������Ă���̂��ɂ��ẮA����A��I�ȋc�_���K�v�ƂȂ낤�B���̂Ȃ�A���ꂪ��Q�҂̎����ɂ���āA���Ƃ������҂����Ȃ��Ƃ��W�F�m�T�C�h�ł���Ƃ����F���������Ă��܂��ꍇ�͂Ƃ������A��O�҂���̓�����A�G�Ύ҂̍��ۓI������Ȃ߂邱�Ƃ�ړI�Ƃ����v���p�K���_�ł���ꍇ����������ł���B�A�[���o�C�W�����l�ƃA�����j�A�l�̊Ԃ̑Η��ɂ����Ă��A�v���p�K���_�ł���Ǝv����咣�����X������Ƃ������Ƃ��ŏ��ɗ��ۂ��Ă��������B
�@�A�[���o�C�W�����l�́A�e�����N��n�A�[���o�C�W�������b���A�����I�ɂ��g���R�l�Ƌ߂����߁A�A�����j�A�l����̓g���R�l�Ɠ��ꎋ����Ă���B�܂��A�\�A�����܂ł́A�A�[���o�C�W�����l�́A���̃e�����N��n�������Ƃ̖��m�ȋ�ʂ��Ȃ��ꂸ�ɁA�^�^�[���l�ƌĂ�Ă����B���̂��߁A�A�[���o�C�W�����ɂ�����s�E���l����ۂɂ́A 1895 �` 96 �N�� 1915 �` 22 �N�ɃI�X�}���鍑�̓��ōs��ꂽ�A�����j�A�l��s�E�ɂ��Ă��l������K�v������B���̂Ȃ�A�A�����j�A�l�͂��̋s�E�̕��Q���A�傫�ȓG�ł���g���R�l�ɑ��Ăł͂Ȃ��A�A�[���o�C�W�����l�ɑ��čs���Ă�������ł���B
�@�܂��A 1905 �` 07 �N�ɃA�����j�A�E�^�^�[���푈���N�����B�w�i�Ƃ��āA�������Ԃ̎Љ�I�K���I�ْ��A���X�����Z���̊Ԃł̍c��̓G�ł���A�����j�A�l�����X�����s�E����ĂĂ���Ƃ����\�Ȃǂ����������A�o�N�[�ł̃n�b�W�E���U�[�E�o�o�C�F�t�E�Q���������ړI�Ȍ����Ƃ���Ă���B�ŏ��́A���X�������d�|�����U���ł��������A�R���I�ȌP����ǂ��Ă����_�V���i�N�}�������ʍU���ɎQ�����邱�Ƃɂ��A���ʓI�Ƀ��X�����ɑ傫�Ȕ�Q���o�āA 3100 �l����P���l�Ƃ������鎀�҂��o������̑������c�A�[���Y���ɐ����Ă���Ƃ����ӎ�������������A�����͓�N�قnjp�����A�A�[���o�C�W�����l�̃A�����j�A�l�ɑ��鑞���͂���Ɋg�債���B
�@1917 �N�̃��V�A�v���̉e�����A 1918 �N�ɂ́A�\���B�G�g�v���ψ���ƃ_�V���i�N�}�̕s����Ȑ��͋ύt�Ɋ�Â��A���ƃA�[���o�C�W�����l�̖�����`���}�ł��郀�T���@�g�}�i�ăg�D���L�Y���j�̑Η����_�@�ƂȂ��āA 3 ��������_�V���i�N�}�̕������A�[���o�C�W�����l���U�����͂��߁A����A���X�����ƃ{���V�F���B�L�̌R���v���ψ���Փ˂��A���������ɂ����s�������߁A 30 ���[���ɁA���X�����̋��Z����V���}�n�Ŋv���ψ���̕��m�ƃ��X����������Ԃɓ���A 31 �� ( �s�E�L�O�� ) �ɂ͎s�X�킪�o�N�[�s�̂قڑS��Ɋg�債�A�_�V���i�N�}���w������A�����j�A�l�����������ʋs�E�ɉ���������Ƃɂ��A���҂̓o�N�[�����ł��A 8,000-12,000 �l�A�A�[���o�C�W�����S�y�ŏ����A�q�����܂ނT���l���]���ɂȂ����Ƃ����A�����̓�����������B�܂��A�A�����j�A�ł��A�u�g���R�l�̂��Ȃ��A�����j�A�v�Ƃ����v��̂��ƂɁA�A�����j�A�ł��A�[���o�C�W�����l�̋s�E��Ǖ����s���A����Ȕ�Q���o���B����ɑ��A 9 ���ɃA�[���o�C�W�����l�������ɏo��ȂǁA�Ȍ�A�������̋s�E�̉��V�͎~�܂�Ȃ��Ȃ�B�����āA���������Ƃ����݁A�����I�Η��̓R�[�J�T�X���ő����A 1918 �` 20 �N�̊ԂɁA�A�����j�A�{���ő����̃A�[���o�C�W�����l���E�Q���ꂽ��A�Ǖ����ꂽ�肵���B 1920 �N�ɃA�[���o�C�W�����Ń\���B�G�g�������������A�R�[�J�T�X�̍������̓��X�N���Ɉς˂�ꂽ���A����ɂ���ăA�[���o�C�W�����̂ƂȂ����i�S���m�E�J���o�t�̒D�҂��A�����j�A�l�͖ڎw���Ă������ƂɂȂ�B
�@�\�A����ɂ́A 1948-53 �N�ɃA�����j�A�̂����ʂ̃A�[���o�C�W�����l���Ǖ�����鎖�������������̂́A�������W�͔�r�I���肵�Ă����B�������A 1965 �N�́u�A�����j�A�l�s�E�\���N�L�O�W������s���v�ȍ~�́A�i�S���m�E�J���o�t�����B�̒D�҂��A�����j�A�l�̏d�v�ȖڕW�ƂȂ��Ă����B
�@�y���X�g���C�J���ɂ́A�A�����j�A�l�ɂƂ��ėl�X�ȍD�s���Ȏ�������A�i�S���m�E�J���o�t�D�҉^���̐����͒��_�ɒB�����B�^���́A�������a���ɍs���Ă������A�₪�Ė\�͓I�ɂȂ�A 87 �N 11 �������� �����̃A�[���o�C�W�����l���A�����j�A��i�S���m��J���o�t���痬�o�����B���{������X���K�C�g�Ɉڑ���������A 2 �� 22 ���ɓ�l�̎Ⴂ�A�[���o�C�W�����l���E�Q���ꂽ�A�V���P�����������N����A�A�����j�A�l�ɑ���A�[���o�C�W�����l�̑�������钆�� 28 ���ɃA�����j�A�l�ɑ���s�E�����Ƃ����X���K�C�g�������N�����i�A�[���o�C�W�����l 6 �l�A�A�����j�A�l 26 �l���S�j�B�{�����͓�̑��������ŁA KGB �ȂǓ��ǂɂ��A�d�������Ƃ������������������邪�A�Ȍ�A�������̖\�͂̉���Ɩ�������ԉ����Ă��܂��A���̉ߒ��ŗ������̑����͑��������B
�@���̂悤�Ȓ��ŃA�����j�A�l�ی�𖼖ڂɁA 1990 �N 1 �� 20 ���A�\�A�R�Ɠ����ȍ����R�̗����� 2 �� 4 ��l���o�N�[�N�U���A���O�� 200 �l���ʋs�E���i�s���s���҂������j�A�S�Ă̊�Ƃ�ڎ����Ĕ�펖�Ԃ�錾�����i�����ꌎ�����j�B�^�̉�����R�͢�A�[���o�C�W�����l�������̉�łƃ\�A�e�n�ŋ}�������Ă����l������ɑ��錩�����߂��������߁A�A�[���o�C�W�����l�̔�Q�҈ӎ������܂����A�v�]���҂̑������������ꂽ �u�p�Y�����̏��H�v�̓A�[���o�C�W�����̋s�E�̃V���{���ɂȂ����B
�@�\�A����̂��A�A�[���o�C�W�����ƃA�����j�A�����ꂼ��Ɨ�����ƁA�A�����j�A�ƃi�S���m�E�J���o�t���������A�\�A�R�̕����b�����g�p����颐���z���̂Ȃ��S�ʐ푈��ɂȂ����B�܂��A���V�A���A�����j�A���x���������Ƃ���`���āi�\�A�� 366 �������^����̓����A 93 �N���� 10 ���h���ɂ����A�����j�A�R�������A�A�[���o�C�W�����̃N�[�f�^�[�x���Ȃǁj�A�A�����j�A���틵��L���ɐi�߂��B 1992 �N 2 �� 25 �` 26 ���̃z�W������s�E�i��ӂ� 613 �l���S�A 421 �l�������A 180 �l�ȏオ�ˑR�s���s���A 1275 �l�ȏオ�l���ɁA 1,000 �l�ȏオ����j�Ȃǂ��o�āA�i�S���m�E�J���o�t�̃A�[���o�C�W���������_�͂܂��Ȃ��ח������B 1992 �N 2 ����� CSCE �i��A OSCE �j�~���X�N�E�O���[�v���a���ɏ��o���������I�Ȑ��ʂ͏o���A�ŏI�I�ɂ� 1994 �N 5 ���Ƀ��V�A�̒���ɂ���퐬�������B�{�����̍ŏI�I�Ȕ�Q�́A���� 3 ���l�ȏ�A�����Җ� 5 ���l�ƂȂ�A �A�����j�A�ƃi�S���m�E�J���o�t����͑S�A�[���o�C�W�����l���Ǖ�����A�A�����j�A�l�̓A�[���o�C�W�����̖� 20 �����̂������Ă���B ��탉�C���ŎU���I�ɔ��C������������̂̒��͈ێ�����Ă��邪�A�a���͓�q���A�A�[���o�C�W�����ɂ������A IDP �i�� 100 ���l�B�A�[���o�C�W�����l�� 8 �l�� 1 �l�j���̌p�����A�A�����j�A�l�ɑ���G�ӂ�����ɑ��������邱�ƂɂȂ��Ă���B
�@�܂Ƃ߂Ƃ��āA���� 1918 �N�ƃ\�A�����̏����̑������w�E�������i�@�w�i�ɕs���ȋ�C�A�A�v���A�y���X�g���C�J�ȂǍ��Ƒ̐��̕ϓ��E�������ɏ悶�đ��������A�B�s�E�͓ˑR�N����A���ړI�����͔��ɍ��ׂȎ����A�C�s�E�����ǂɐ����Ă���\���A�D��x�A�s�E���n�܂�ƁA�G�X�J���[�g���A��s�E�ւƔ��W�A�E�s�E�̉ߒ��őo���̓G�ӁE���������������j�B���ɁA�A�[���o�C�W�������{�́A�W�F�m�T�C�h�L�O����l�X�ȕȂǂɂ���āA���݂̐����o�ϖ��A���ƁA����Ȃnj������ւ̍����̕s�����A�����j�A�l�ɐU������A�܂��i�V���i���Y�������g�����A�W�F�m�T�C�h������ɗ��p���Ă���Ƃ����_������B��O�ɁA���ێЉ���n�̕��a�\�z�ɑ����͂ł���A�v���p�K���_�̔F�����Ƃ�����ŁA�e�n�̖����Η����������Ă��������ł̕�I�ȋc�_���K�v���ƍl����B�����Ԃ̖��̍��{�����Ƒ������������Ȃ�����A�s�E�͊e�n�ō�����J��Ԃ����\��������B
 �v�|�A�F�@���S���q�i������w�j
�v�|�A�F�@���S���q�i������w�j
�u�}�C�m���e�B�̌����̍��ۓI�ۏ�v
�͂��߂�
�@�}�C�m���e�B�̕ی�́A���ېl���@�̔��W�j�ɂ�����Â��ĐV�����ۑ�ł���B����͓����ɁA���A�̂��Ƃő傫�Ȕ��W�𐋂������ېl���@�Ƃ��̕ۏ�V�X�e���ɓ��݂���ő�̎�_�ł�����B�ȉ��ɁA�}�C�m���e�B�̌����̍��ۓI�ۏ�ɂ��ė��j����ь��s�̖@�Ɛ��x���T�ς���B
�E ���ۘA���̃}�C�m���e�B�ی쐧�x
�@�}�C�m���e�B�̖��́A��l����T�O�����܂��ȑO�ɂ��łɍ��ې����Ɩ@�̖��ł������B 17 ���I�A���ۖ@�̗h�Պ��̃��[���b�p�ł́A�@�����v�Ɓu 30 �N�푈�v���_�@�ɏ@���I�}�C�m���e�B�̕ی�Ɋւ��������ԂŌ��킳��Ă����B�l���v�z���J�Ԃ��� 18 ���I���o�� 19 ���I�ɂ́A�ꕔ�̖����I�}�C�m���e�B���ی�̑ΏۂƂ��ꂽ�B���ێЉ�}�C�m���e�B�̌�����ۏႷ���Ăɒ��肵���̂́A��ꎟ���E����̂��Ƃł���B���ۘA���́A��ꎟ���E���s�퍑�ƒ鍑��̌㐬�������V�����ƂɁA�����́u�l��I�܂��͖����I�i national �j�}�C�m���e�B�v�k���P�F�e national '�͑��`�I�ł���A������肵�Ȃ����{�e�ł́A������I��ƖB�l�̕ی�����ɂ���ċ`���t���A���̎��{���Ď������B�����A�卑���͂ɂ���ē��荑�ɋ��v�����K�͂́A��ʐ��E���Ր�������Ȃ������B���̎�ړI���A 17 ���I�ȗ��̉c�݂Ɠ��l�A���B�̍��ƊԊW�Ɗe�����̈��肨��ђ����ێ��ł����āA�l���̎��_�͎ォ�����B�Ƃ͂����A���Y�̏��ɂ́A�ʌ����A�W�c�I�Ǝ����̕ێ��Ɋւ��u���ʂȌ����v�A�l�̌����̏W�c�I�s�g�A���Ƃ̐ϋɓI�[�u�`���Ȃlj���I�ȓ��e�̋K�肪�u����Ă���B�����N�Q�Ɋւ���l�ʕ�葱���i��������̐\�����āj���܂ޏ�s�m�ۂ̎d�g�݁A���̈ꕔ��S������ݍ��ێi�@�ٔ����ɂ���ĂȂ��ꂽ�}�C�m���e�B�̌����Ɋւ���i�@�I���f�⊩���I�ӌ��Ȃǂ́A����ȍ~�̍��ېl���ۏ�̔��W�ɏ��Ȃ��炸��^�����B
�E ���A�̃}�C�m���e�B�ی�V�X�e��
�@�l�����d��ړI�̈�Ɍf���Đݗ����ꂽ���A�́A�A���̃}�C�m���e�B�ی쐧�x���p�����Ȃ������B���ՓI�l���̔ʕ����K�p�ɂ���ă}�C�m���e�B�ɑ�����l�X���ی삳���Ƃ����l�����A�܂�������`�I�ȍ��������u�������ێЉ�Ŏx�z�I�ł������B�l����肪�A�����I�Ɋe���̍����������獑�ۓI�S�����ɕω������Ƃ͂����A�W�c�̖��E��h�~�E��������W�F�m�T�C�h���̍���ȊO�ɂ́A�������̐l�����Ɋ֘A����K�肪�u���ꂽ�����ŁA�}�C�m���e�B�͒��ڂ���邱�Ƃ����Ȃ������������������B���݁A�}�C�m���e�B�̌������K�肷���v�ȍ��A�����́A�u�s���I�E�����I�����Ɋւ��鍑�ۋK��v�� 27 ���Ɓu�����I�i national or ethnic �j�A�@���I����ь���I�}�C�m���e�B�ɑ�����҂̌����Ɋւ���錾�v�i 1992 �N���A����c�B�ȉ��A��錾��j�ł���B��҂͖@�I�S���͂�����Ȃ��Ƃ͂����A�������e�ƍ��Ƃ̋`�������Ȃ�ڂ����K�肷���I�����ł���B�Y������}�C�m���e�B�̍\�����͓��L�̌����A���Ȃ킿�W�c�I�Ǝ����̈ێ��E���W�Ɋւ�镶���I�����A�Љ���⌈��ߒ��֎Q�����錠�������L���A�W�c�I�s�g���F�߂���B�@���Ƃ͗l���܂ȐϋɓI�[�u���u����`�����B
�@�_���ɖ����������̋N����ƂƁA���̌�A��Ɍ������������قƂ�ǂȂ����Ƃ́A�����Ɨ��E�����������𖾕��Ŕے肵�Ă��Ȃ��A�}�C�m���e�B�ւ̌����t�^�ƏW�c�I�ی�ɑ��鏔�����{�̌x���S�������ɋ������������Ă���B�k���Q�F��Z���������錾�����l�̒�R�ɂ����Ē��ɕ����Ă���B���ۖ@��A��Z�����̓}�C�m���e�B�Ƃ͋�ʂ���A���̐�Z���䂦�Ƀ}�C�m���e�B�����錠�������ƍl������B���炪�]�ޏꍇ�ɂ́A��Z�����̓}�C�m���e�B�̌������咣�E�s�g�ł���B�l����ł��錾�̐����́A���ێЉ�A���ՓI�l���̔ʕ����K�p�����ł̓}�C�m���e�B���\���ɕی�ł��Ȃ����ƁA���ʁE�}���E�r���E�����I��������͗̓y�ۑS�ƍ����������������ĕs����ɂ�����ʂ������Ƃ��o���I�Ɋw�сA�ނ��둽���������ɂ���ĎЉ�����肳����ׂ����ƂɋC�t�������Ƃ������Ă���B
�E�܂Ƃ߂ɑウ��
�@�����閯�������Ɍ��炸�A�n���A�J���A����A�ی��A���A��A�ڏZ�J���A�l�g�����ȂǁA�n���I�ۑ�̂قƂ�ǂ̓}�C�m���e�B���ł���B�Ƃ��ɋߔN�A�}�C�m���e�B�̑����́A��������э��ƊԂ̊i�����g�傳����o�ϓI�O���[�o�����̘c�݂ɒ�������A���邢�͢���e���푈��Ƃ������̉��̐����I�}���̋����ɂ���āA��w�̍���ɒ��ʂ��Ă���B���������������̐i�W�Ɠ����҂̋��A�[���s���ƃj�[�Y�ɑ��A���ێЉ�̑Ή��͋ɂ߂ĕs�\���ł���B�u�l�̌����v�ւ̂������́A�W�c���A�N�^�[�E���ΏۂƔF�߂邱�Ƃ�W�c�Ԃ̊i��������W����B�ۏႳ��錠���͕����I���������S�ł����āA���|�I�����̃}�C�m���e�B���K�v�Ƃ���n������̒E�p�Ǝ����̍Ĕz���͍��Ƃɋ`���t�����Ă��Ȃ��B�����ɂ��ẮA�T�ˎ���I�\�������I��I�\�Ή��ɂƂǂ܂�A�����x��Ɩh�~�̐��x�͖������ł���B
�@�u�W�F���_�[�̎嗬���v�Ɠ��l�ɁA�e���ƍ��A�̂��ׂĂ̊�������Ɉӎ��I�Ƀ}�C�m���e�B�̎��_�����邱�Ƃ��K�v���d�v�ł���B����́A�W�c�Ԃْ̋��ƑΗ������炵�A���������{�I�ɖh�~���邱�ƂɂȂ���ł����ʓI�ȕ���ł����낤�B
--------------------------------------------------------------
�k�Q�l�����l
���@���M�u���ېl���@�ƃ}�C�m���e�B�̌����v���ۖ@�w��ҁw���{�ƍ��ۖ@�� 100 �N�A�� 4 ���A�l���x�i�O�ȓ��A�Q�O�O�P�j
�����ʍ��ۉ^�����{�ψ���ҁw�}�C�m���e�B�̌����Ƃ́x�i����o�ŎЁA�Q�O�O�S�N�j