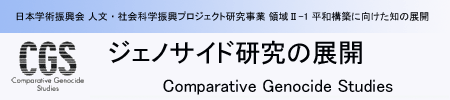第1回 CGSワークショップ
「「文化ジェノサイド」と日本の朝鮮支配」
*「ジェノサイド論の系譜」班・「東北アジア」班 合同開催
日程・会場他
・日時: 2004年2月23日(月) 15:00〜17:30
・場所:東京大学駒場キャンパス アドミニストレーション棟3階 第3‐4会議室
◇司会: 石田勇治(東京大学)
■報告者: 松村由子(東京大学・院)
報告要旨
本報告は「ジェノサイド研究の展開」プロジェクトが提起する「広義のジェノサイド」の一つとして文化(的)ジェノサイドの概念を整理し、その研究可能性を模索するものである。
「ジェノサイド」という言葉を創造した法学者レムキンは、彼の著書でジェノサイドが行われる領域として政治、社会、経済と並んで文化領域を挙げている。これは自国言語使用の禁止、高等教育機会の奪取、文化・芸術活動の制限、記念碑・文書館の撤去等を表す。国連ジェノサイド条約( 1948 )ではこの文化領域におけるジェノサイドは罪として定義されず、国際刑事裁判所規程( 1998 )においても同様であった。国連での条約採択過程で文化ジェノサイドを定義に盛り込むべきだと主張したソヴィエトは自国の百科事典の「ジェノサイド」の項目に「民族および文化ジェノサイド」を併記し、反対の態度を示したフランスも国内百科事典では文化の破壊を意図する行為をジェノサイドの罪と明記している。この「文化ジェノサイド( cultural genocide )」はほかに「 symbolic genocide 」、「 white genocide 」、「 ethnocide 」などの言葉で表現され、身体的( phisical )、実際的( actual )な破壊行為と対にされて研究書等の記述に用いられている。
ニュルンベルク裁判を経てジェノサイドを国際法上の犯罪とする努力が払われる。レムキンを含む条約起草担当者3名を中心に、条約草案の準備要請決議( 1946 )から条約採択( 1948 )までおよそ2年にわたる議論が行われた。 1947 年 6 月の経済社会理事会での草案ではジェノサイドは身体的、生物学的、文化的という三つの類型で示され、集団を代表する個人の強制・組織的追放、民族言語の使用禁止、書籍等の破壊や出版の禁止、また記念建造物や文書の破壊などがジェノサイドの行為とみなされた。概念を拡大しすぎとする懸念に対し、レムキンは文化ジェノサイドの条約への取り込みを強固に主張した。文化ジェノサイドを条約に入れるか否かは処罰すべき国際法上の犯罪として規定するか否かの問題であり、そのためには範囲と定義の曖昧さ、他の条約との関わり、文明化の努力への阻害などの点を克服する必要があった。同時にこれらの議論には、各国の国内少数者政策などとの関わりが指摘されている。
ジェノサイド研究との関係を言うならば、ナチス・ホロコーストの「ユニーク」性を主張する議論ではジェノサイドの範囲は限定される。トルコのアルメニア人虐殺、ドイツのユダヤ人およびシンティ=ロマの虐殺、そしてルワンダのフツ族?ツチ族間虐殺だけがジェノサイドであるとする見方もある。一方、ホロコースト相対化の議論ではジェノサイドの広い解釈がなされ、原因の類型化や諸局面を表す新語の登場とともに文化ジェノサイド概念の普及と議論が行われる。ここでジェノサイドとエスノサイドとの関係が取り沙汰されるが、主としてレムキンの解釈や定義の論争に終始している。ここには法概念と道徳概念とのギャップがある。
文化ジェノサイドを歴史的事例に則して見てみると、発生の背景や方法に共通のパターンがある。背景としては占領・植民地支配、国内「異民族」に対する政策、(身体的/生物学的)ジェノサイドがある。そして戦争によっても文化ジェノサイドは強化されていく。方法としては同化政策や「文明化」による生活様式の強要が多く見られるが、「近代化」、「統合」などの名目で要求される変化は社会の内部論理を無視し、結果的に社会的矛盾や文化的衰退を招く。さらに占領・植民地支配では多く現地調査や研究が行われるがその理解は大抵曖昧で、相手を劣等視し、その生活様式を卑下する。身体的/生物学的ジェノサイド下ではその終着としての文化ジェノサイドが行われる。日本の朝鮮支配では戦争によって朝鮮人に対する「皇民化」政策が強化されていった。ドイツのポーランド支配( 1939 ? 1945 )、日本の朝鮮支配( 1910 ? 1945 )においては言語の禁止、地名・人名の改称、高等教育からの現地人の排除などが共通してみられ、そのほか文化施設の破壊、信仰の強制、文化学習のすり替えなどが行われる。レムキンが根拠としたドイツの文化ジェノサイド事例は比較研究を行う場合に無視することはできない。
植民地化とは「必然的に文化ジェノサイドの行為である」とするサルトルの言葉があるが、日本の朝鮮支配は精神的・文化的な面にも力点をおき、文化・教育面における同化政策は朝鮮民族の独自性を抹殺するものであった。例えばいわゆる創氏改名は単に朝鮮人から名前を奪い、アイデンティティを奪うだけでなく、朝鮮の伝統的家族体系を崩壊させるものであった。日本の朝鮮支配の特徴の一つとして、支配者の朝鮮に対する「植民地」認識の欠如があり、朝鮮人に対する「異民族」認識の欠如が指摘できる。ゆえに支配者たちに朝鮮民族殲滅の意図があったかどうかを証明することは難しい。このことは日本の事例を文化ジェノサイドとしてとらえ、比較するためには克服しなければならない課題である。
身体的/生物学的ジェノサイドが「民族浄化」概念との相違の説明を求められるのと同様に、文化ジェノサイドについてもエスノサイドや文化帝国主義などといった文化抑圧の他の概念との相違を説明する必要がある。ユネスコは「サンホセ宣言」( 1981 )において、エスノサイドと文化ジェノサイドを同一視することを試みている。報告者の見解としてはこの二つは同じ事象の表裏の関係であり、被害者側の結果から見ているか、行為者(加害者)側の意図(原因)から見ているかの違いである。また文化帝国主義についてはすでにサイードやトムリンソンなどの研究があり、それと文化ジェノサイドとの関係については報告の機会を次に譲りたい。
主要参考文献(出版年順)
・UN Doc. E/447 (1947)
・ A/C. 6/SR (1948)
・ E/AC. 25/SR (1948)
・ Rapha ё l Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Law of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress, Howard Fertig, Inc. Edition, New York , 1973.
・ Leo Kuper, Genocide: Its Political Use in the Twentieth Century , Middlesex, 1981. (レオ・クーパー(高尾利数訳)『ジェノサイド?? 20 世紀におけるその現実??』法政大学出版局、 1986 年。)
・ Israel W. Charny, ed., Genocide: A Critical Bibliographic Review , London , 1988.
・ James Crawford, The Rights of Peoples , Oxford, 1988
・ George J. Andreopoulos, ed., Genocide: Conceptual and Historical Dimensions , Philadelphia , 1994.
・ Samuel Totten/ William S. Parsons/ Israel W. Charny, ed., Genocide in the Twentieth Century: Critical Essays and Eyewitness Accounts , New York / London , 1995.
・ Steven R. Ratner/ Jason S. Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities in International Law: Beyond the Nuremberg Legacy , Oxford , 1997.
・ Levon Chorbajian/ George Shirinian, ed., Studies in Comparative Genocide , New York, 1999.
・ William A. Schabas, Genocide in International Law: The Crimes of Crimes , Cambridge , 2000.
・ Alexander Laban Hinton, ed., Genocide: An Anthropological Reader , Oxford/ Massachusetts, 2002.
・ David Hirsh, Law against Genocide: Cosmopolitan Trials , London, 2003.
・ J-P ・サルトル(海老坂武解説)『植民地の問題』人文書院、 2000 年。
・前田朗『ジェノサイド論 "Genocide and Genocidal Rape"』青木書店、 2002 年。
「文化ジェノサイド」と日本の朝鮮支配 (討論)
創設シンポジウムとそれに続く意見交換の中からでてきた重要な問題提起に、[主として]人間の生命を奪う行為(ジェノサイド)が人間から言葉を奪う行為(「文化ジェノサイド」)と同列に論じられてよいのか、また「文化ジェノサイド」という概念を使用することでジェノサイド本来の意味とインパクトが損なわれ、「概念としてのジェノサイドのインフレ」を招くのではないかというものがある。今回のワークショップでは、こうした問題提起を受けて、あえて「文化ジェノサイド」を表題に掲げる研究報告が行われた。
報告後の討論では概念の問題に議論が集中した。その論点は大きく次の二点に集約される。
- 「文化ジェノサイド」は、従来の研究で使われてきた用語( Ex. 「民族文化抹殺」)とどう違うか。
- 「文化ジェノサイド」にあたるかどうかを判定する基準は何か。
この二つの問いはともに、これまで「占領政策」「マイノリティの同化・抑圧」などの枠組で扱われてきた問題に対して、新たに「文化ジェノサイド」という分析概念を導入することの意義と有効性を問うものでもある。
討論では、「民族抹殺」「民族文化抹殺」というような、東北アジアの文脈で用いられることの多い用語とは異なり、「文化ジェノサイド」はヨーロッパ、アフリカ、アジア、南北アメリカなど20世紀に世界各地でみられた類似の現象を比較検討する可能性をもつ概念であるとの意見がだされた。たとえばアフリカ研究者からは、ルワンダでは 1990 年代のジェノサイドが植民地時代に強制された社会システム変容と明らかに関連しているが、身体的・生物学的ジェノサイドと文化的ジェノサイドの連関という視点を他地域に適用し、共通の分析枠組みとすることは可能かとの問いかけもなされた。なお、報告者は「文化ジェノサイド」の主要な基準として「言語」に注目しているが、文字の普及率など言語状況には地域差が大きい。「文化ジェノサイド」が地域横断的な分析の可能性を有する概念であるだけに、概念規定においても分析対象とする局面の選択においても各地域の実際の状況に対する行き届いた目配りが必要になろう。
「文化ジェノサイド」を「外部勢力による文化変容の強制」と考える場合、注意すべきはグレーゾーンの問題である。
- 土着の文化が外部勢力によって強制的に変容させられるという意味では、真っ先に植民地の近代化の問題が射程に入る。その際、近代化(のために導入された公的制度)そのものに問題があるのか、近代化の方法に問題があるのかという判断が必要になるが、グレーゾーンも大きい。
- 植民地の状況、国民統合強化の流れの中でのマイノリティの状況について、(表面的には)自主的に文化を捨てていくという現象が確認される場合もある。
討論で指摘されたこれらのグレーゾーンの存在は論点として興味深いものであり、より緻密な分析への糸口となろう。
今回の報告は、とくに日本の植民地支配に対して「文化ジェノサイド」概念を適用する可能性を検討するものであった。その点については以下のような質問・意見が出された。
- 日本の朝鮮支配は、たとえば琉球、台湾、アイヌに対する日本の政策とどのように関連していたのか。また違いは何か。
- 日本の台湾支配、朝鮮支配の全局面が「文化ジェノサイド」であったと言うのは難しいのではないか。
- 自らの言語を奪われ、支配者の言語を強制されるという状況の中で、受容者がたくましく抵抗していったという面も見過ごしてはならないだろう。
討論を通じて、「文化ジェノサイド」概念について今後も議論を深めていくことの重要性とともに、概念をめぐる議論は個別事例研究の積み上げによる裏付けをえてはじめて意味あるものとなるであろうことが改めて確認された。